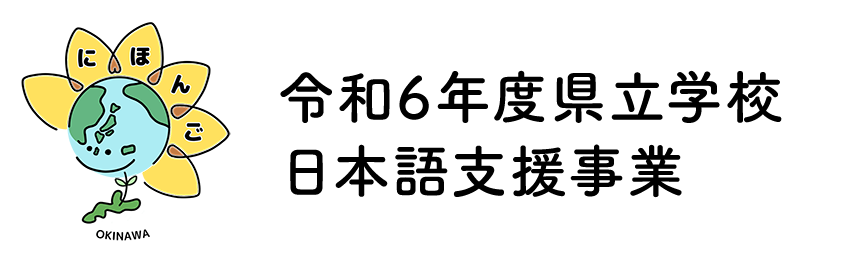キャリア支援・居場所支援
nihongo
キャリア支援・居場所支援
日本語支援とは、日本語を指導することだけではありません。生徒が安心して学習に向かうための「居場所支援」や、卒業後どのように生きていくかを考える「キャリア支援」も含め、包括的に支援することが大切です。
慣れない文化の中で生活することは、想像以上にストレスを感じます。外国につながる生徒は、日本へ来た背景、時期、そして日本語力もさまざまです。ほとんどの場合、保護者の都合によって来日しているため、子ども本人の意思で来たわけではないということを前提に考える必要があります。
日本で生活し、日本の学校に通うためには日本語を習得することが必要ですが、習得過程では、自分の伝えたいことを日本語で表現できずにもどかしく思ったり、周囲が理解してくれないという疎外感を感じることがあります。
日本語に関すること以外でも例えば、

といった声もあります。
そのような生徒が安心・安全に学校へ通い学習に向かうための環境づくりも重要な支援のひとつです。
生徒が安心して支援を受けるうえで、支援者との信頼関係が必要不可欠です。日々の学校での支援において生徒に寄り添い、必要に応じて生徒が慣れ親しんだ言語で支援することもあります。これまで自分の言葉が周りになかなか通じずにいた生徒が、支援員が入ることでいきいきと自分の話をするようになったとの声もありました。
高校生になると、将来について具体的に考えるようになりますが、外国につながる生徒の場合、言語の壁や文化の壁、保護者の日本社会経験、就労状況等が課題になることが少なくありません。地域社会の受け入れ環境の整備も求められます。
また、学校と家庭だけでなく、サードプレイスから、地域社会への参加、社会性の獲得につなげます。
居場所支援、キャリア支援は、包括的な支援として、生徒自身が主体的に活動することを促進し、民主的な社会の形成者、主権者として成長するために大切な教育支援だと考えます。その取り組みには、学校内外での連携、保護者・家庭との連携が必須です。
居場所・キャリア取り組み事例
○ 生徒とのコミュニケーション
個別面談を通して、学校や家庭での困りごとを聞き取ったり、支援の要望や生徒の目標を一緒に確認したりします。また、生徒が卒業後どのような進路を希望しているのかを聞き取ります。進路が未定の生徒に対しては、自分の将来を考えるきっかけとして、「20歳の時に自分はどこにいるのかをイメージしている?」等を問いかけたりします。また、生徒の母語で何気ない雑談をしたり相談を受けたりすることもあります。それらを担任の先生に共有することで、生徒理解や安心感につながったという声もありました。
○ 保護者とのコミュニケーション
卒業後の進路や今後の支援について考えるためには、保護者との面談も重要です。生徒と保護者それぞれに希望する進路を聞き取り、その支援に向けてどういった支援をする必要があるのか再確認および計画をします。外国籍の生徒には進路を考えるうえで重要なビザの確認もします。必要に応じて、保護者面談に必要な資料(単位の仕組みや学校規則など)の翻訳も行います。また、日本語支援員が同席して学校での支援の様子を伝えたり、家庭での困りごとがないか等を聞き取ったりします。日本語が母語ではない保護者との電話連絡に対応することもあります。
○ 発達評価
支援開始前に実施する「はじめのチェック」(発達の問題の有無や、日本語力把握のためのペーパーテスト)において、日本語習得に支障をきたすような発達の問題(知的発達の遅れ、学習障害、ADHDなどを含む)があることが疑われた場合に、本人及びご家族の同意を得て、言語聴覚士が発達検査を実施し問題を明らかにしていきます。発達の評価結果、及び生徒の特性や性格なども考慮し、今後必要となる学習支援・包括的支援について提案します。

○ 交流会
生徒同士のコミュニケーションを図るために交流会を実施し、その際にゲストスピーカーを招いて異文化の中で暮らした経験のある先輩の話を聞くこともあります。交流会を通して、自己開示、他者理解、相互理解を深めながら、自己肯定感を高められればと考えます。
○ キャリア支援
異文化の中で暮らした経験談やチャレンジストーリーを聞く交流会や自分の強みやチャームポイントを考えるオンライントーク、またオープンキャンパスに関する意識調査等を包括的に行いました。生徒それぞれの希望や必要なタイミングに合わせ、オンラインや対面にて実施しました。支援員と一緒に志望する大学に提出するエントリーシート作成支援を受け、自分を伝えるための文章表現を学び、「楽しかった」とコメントしたZさんは、日頃の努力が実り、無事志望大学に合格しました。また、高校卒業後にホテルへの就職を希望している生徒に対して、面接時によく聞かれる質問を支援員が作成し、コーディネーターと一緒に面接練習を行いました。